ロコモティブシンドロームの予防方法と、その実態について解説します。
- 2025.05.06
- 健康
- ロコモティブシンドローム, ロコモ予防

あなたは、「ロコモティブシンドローム」という言葉をご存じですか?
実は私も、言葉さえ聞いたことはあるもののちゃんとした意味は知りませんでした。
年齢を重ねるごとに増加傾向にあるこの症状は、運動機能の低下がもたらす様々な症状を引き起こします。
それによって、日常生活や健康に大きな影響を与えると考えられます。
今回この記事では、ロコモティブシンドロームの基本的な知識や発症のメカニズム
それと私が、普段から予防策として行っていることを徹底的に解説していきます。
いつまでも健康で元気に暮らせるように、ロコモティブシンドローム対策していきましょう。
目次
ロコモティブシンドロームとは?

ロコモティブシンドロームとは、年齢に伴う衰えで筋力の低下や、関節や骨の疾患などによって
移動能力が、低下してしまう状態のことを指して言います。
私が勤める介護施設でも、60代半ばで車いす生活を余儀なくされている方もいる一方で
90代に入っても、しっかりと自分で歩いている方もいらっしゃいます。
この差は一体何なのだろうと、良く思う時があります。
出来ればいつまでも、しっかりと自分の足で歩いていたいものです。
それは、毎日の生活の積み重ねが大事になってきます。
ロコモティブシンドロームのことを考え、生活改善に努めましょう。
ロコモティブシンドロームの予防方法

ロコモティブシンドロームを予防方法するには、適度な運動とバランスの取れた食生活が大切です。
ロコモティブシンドロームとは、筋肉や関節または骨などと運動機能の衰えにより
歩行や立ち上がりなどの基本的動作が、困難になることです。
年齢とともに、筋力や骨密度などが下がってしまいますと、転倒や骨折のリスクが高まり
要介護になりうる可能性も、高まってしまいます。
若いうちから、筋力を鍛え栄養のバランスを整えることが鍵になります。
例えば、運動ならスクワットやウォーキングなどあまり激しくなく、長く続けられるも
栄養面で言いますと、カルシウムやビタミンDを多く含む食品を摂取して
週に一度は、ストレッチや柔軟体操をすれば関節の柔軟性維持にも繋がります。
つまり、ロコモティブシンドロームを防ぐためには、「毎日の運動」と「栄養」の大切さを視野に入れ、継続することが最も大切です。
このことを少しでも意識することで、あなたもきっといつまでも若々しくいられるはずです。
ロコモティブシンドロームと介護の関係性

ロコモティブシンドロームは、将来介護が必要となる大きな原因のひとつであります。
予防をすることで、介護度が軽減したり、介護の必要となる時期を遅らせたりします。
ロコモティブシンドロームは、加齢や運動不足で筋肉や骨関節が衰え、移動機能が低下する状態です。
移動機能が低下しますと、転倒や骨折のリスクが高まり、要介護または寝たきりににもなりかねません。
私は、介護施設で働いていますが60代でもう車いす生活の方、90代でも自分で歩いている方
そういった人を見ていますと、生活スタイルで変わるのだなと実感します。
つまり、ロコモティブシンドロームを予防改善することによって、
将来的な介護リスクを減らすことに繋がります。
まとめ
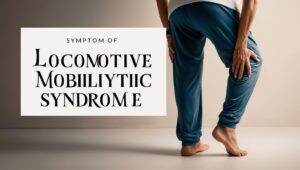
ロコモティブシンドロームは「自分にはまだ早い」と思っているうちに進行してしまう。
だからこそ、40代50代から予防を始めておいくのがちょうどいいでしょう。
私ももう50代後半にもなりますので、切実な問題となってきました。
さらに生活習慣を見つめ直して、将来に備えたいと思います。
自分の足で好きな場所に出かけ、健康的な生活が続けられるために
あなたも、今日から小さな一歩を踏み出してみましょう!
-
前の記事
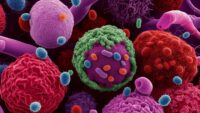
口内フローラ革命、健康と美しさを守る習慣はズバリこれです! 2025.04.28
-
次の記事

50代にして痛風の症状が出た私が、対処方法について向き合っていきます。 2025.06.06